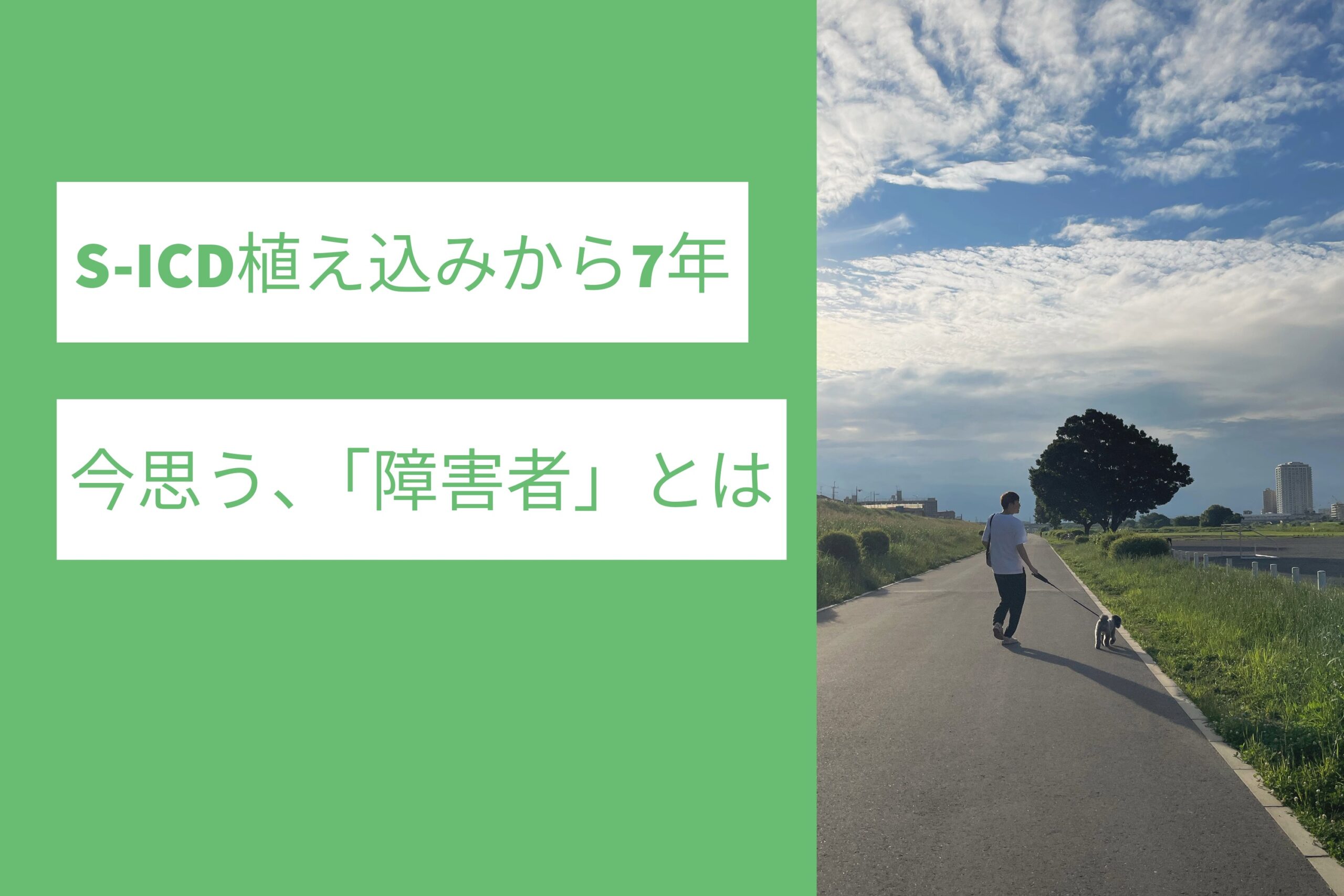公開日 2025年10月31日 最終更新日 2025年11月1日
以前の記事でS-ICDの植込み手術について書きましたが、先日29歳になり、そろそろ入れ替え手術の時期が近づいてきました。
最初の手術を受けたのが22歳の時。主治医からは「電池の寿命は6〜7年程度だから、その頃に入れ替え手術をすることになるよ」と言われていました。実際に今年5月の定期通院で充電残量を確認したところ、20%近くまで減っていました。主治医から直接「来年手術」とは言われていませんが、過去の話と現在の充電量を考えると、来年中には手術になるんじゃないかと思っています。そろそろ気持ちの準備をしていかないといけません。
7年前、いきなり障害者になった時は、これからどうなるのか全く想像できませんでした。でも実際に過ごしてみると、思っていたのとはだいぶ違う7年間でした。今回は、その辺りのことを書いてみようと思います。
はとらくでは、心臓病に関する寄稿を募集しています。当事者や医療・福祉の現場にいる方の声を、編集部がサポートのうえ発信しています。
【目次】
あっさりと障害者になった日
退院後、障害者手帳を取得するために役所へ行きました。もっと大げさな手続きなのかと思っていましたが、実際は拍子抜けするほど淡々としていました。
窓口で必要書類を提出して、待つこと30分ほど。名前を呼ばれて窓口に行くと、まるで住民票でも渡されるかのように、あっさりと障害者手帳を渡されました。分厚い冊子(福祉サービスの案内)と一通りの説明はもらいましたが、手続き全体でも1時間もかからない程度。この短時間で、自分は健常者から障害者になりました。いや、書類上そうなっただけで、実感なんて全く湧きませんでした。
そもそも「障害者雇用」というルール自体、知らなかったほど。企業に障害者を雇用する義務があることも、障害者枠という採用枠があることも、全く知りませんでした。退院後、親戚から「障害者雇用っていう選択肢もあるよ」と言われてはじめて知りました。まさかその後、自分が障害者の就労支援をする側に回ることになるとは、この時は想像もしていませんでした。
周りの反応も、予想とは違いました。倒れたこと自体については、みんなすごく心配していたんですが、「障害者になった」と伝えても、あまりピンときていない感じでした。S-ICDが入っていると説明しても、見た目は変わらないし、普通に歩いているし、話もできる。内部障害の伝わりにくさ、この時はじめて実感しました。
ただ、結局のところ、自分の日常は大きく変わりませんでした。(プランクは永久に禁止になりましたが)。でも友人との付き合い方も、趣味も、基本的には以前と同じ。生活への影響が少ない内部障害だったことも関係していると思いますが、自分自身も周りの人も、本質的には何も変わらなかったんです。
就労支援で知った障害者雇用の現実
でも、障害者雇用専門の転職エージェントで働き始めてから、「障害者として生きる」ことの別の側面を知ることになりました。
相談に来る方々の状況は、想像以上に厳しいものでした。
1年以上求職活動をしているけど就職できない人。せっかく入れた会社だけど、聞いていた話と違って心身への負担が大きくなり退職した人。1つの職種で長年キャリアを積み重ねてきたけど、障害を持ったことでその仕事ができなくなり、「今までの経験がリセットされた気がする」と悩む人。
私のように「日常があまり変わらなかった」なんて言える人は、実は相当恵まれているのかもしれないと思いました。
一方で、企業側の苦悩も見えてきました。年々法定雇用率は上昇しています。企業はその影響もあるし、そもそもの考え方の変化もあり、障害者を採用することに積極的になっている傾向はあります。ただ、現実は追いついていません。バリアフリー設備の整備が間に合わない、現場での障害理解を深めるための教育体制が整っていない、配慮事項への対応方法がわからない。採用数を増やしたい気持ちはあるのに、受け入れ体制が追いつかないという板挟みになっている企業が少なくありません。
年々、障害者雇用への注目度は徐々に高まってきています。でも、まだまだ改善するべきことが多く残っているのが現実です。
「障害者だからわかる」という思い込み
転職エージェントで働き始めた頃、自分にはある種の自信がありました。「自分自身が障害者だから、健常者だった頃より、他の障害者の人の気持ちがわかるはず」という自信です。
でも、これは完全に思い上がりでした。
障害者と一口に言っても、障害内容も程度の重さも、そもそもの個人の性格も、みんな違います。視覚障害の方の不便さは、S-ICDを入れている私には本当の意味では理解できません。精神障害で苦しむ方の辛さも、発達障害の方が感じる生きづらさも、私の経験からは想像することしかできません。
同じ心臓障害の方でも、症状も生活への影響も全然違います。ペースメーカーの方、人工弁の方、私のようにS-ICDの方。それぞれに違う配慮が必要で、違う不安を抱えています。
結局、「自分が障害者になっただけで障害者の気持ちがわかる」なんてのは甘い考えでした。大切なのは「障害者」というカテゴリーで理解しようとすることではなく、目の前にいる相手個人を理解しようとすること。これは障害の有無に関係なく、人と向き合う時の基本中の基本でした。恥ずかしながら、障害者になって、転職エージェントで働いて、やっとそのことに気づいたんです。
7年経って思うこと
22歳で突然障害者になり、29歳になった今、S-ICDの入れ替え手術を控えています。この7年間は、想像していたよりもずっと「普通」で、でも同時に多くの学びがありました。
障害者になることは、確かに人生の大きな転機です。でも、それで人生が終わるわけではない。むしろ、新しい視点を得て、違う世界が見えてくることもある。私の場合は、障害者雇用の仕事を通じて、社会の課題や人の強さ、優しさを知ることができました。
来年には入れ替え手術を受けることになるでしょう。正直、前回の手術の痛みを思い出すと憂鬱です(痛みに弱いんです、本当に)。でもこれも自分の人生の一部。新しいS-ICDと共に、30代を迎える準備をしていこうと思います。
次の7年後、36歳の自分はどんなことを思っているんでしょうか。その頃には「入れ替え手術?2回目だから余裕でしたよ」なんて言えるようになっているといいなと思います。